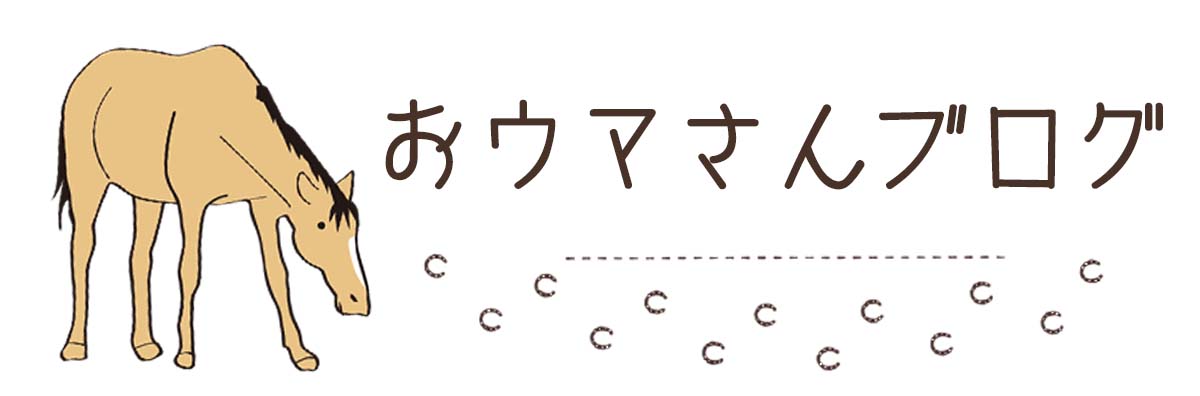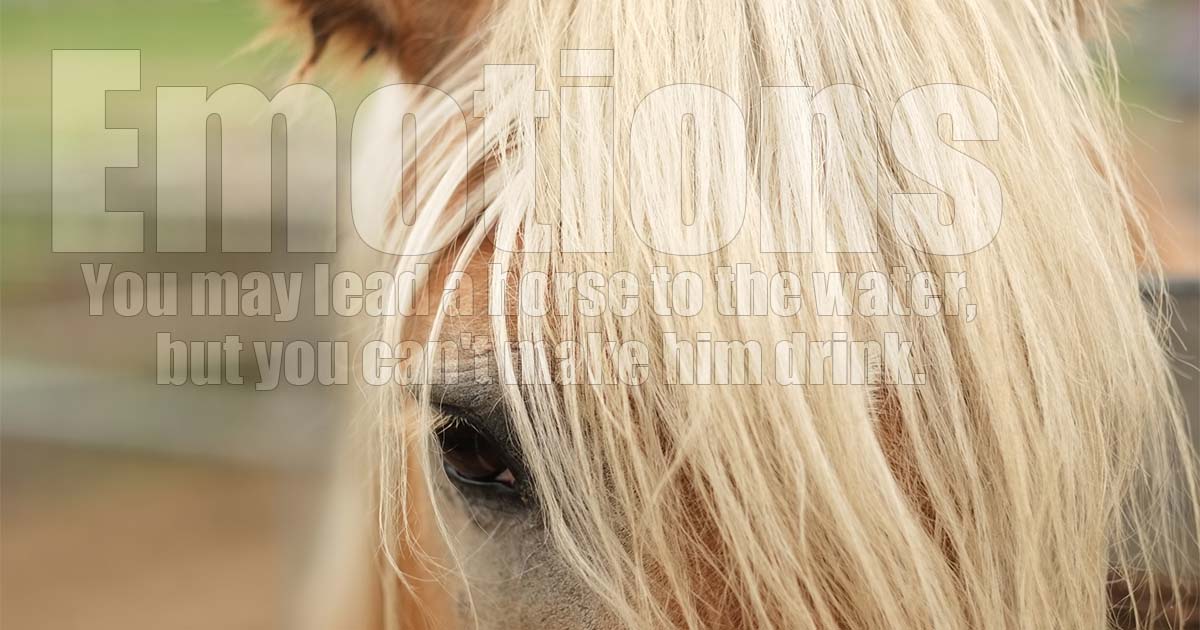今回はちょっと真面目なお話です!
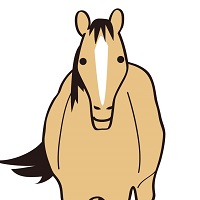
今回のおウマの出番はこれだけ…
馬を水辺につれて行くことはできても
水を飲ませることはできない
英語のことわざである『You may lead a horse to the water, but you can’t make him drink.』からきた言葉です。
今回お話しする内容は、この言葉にすべて集約されています。
タイトルの通り、『馬は感情で走る生き物』です。
血統や馬体のバランスなんてものは能力の底上げに過ぎず、馬が競馬において一生懸命に走るのは、そこに馬の意志があるからです。
それは、太古の昔より、競走して群れの中での優劣をつけていた名残かもしれません。
それは、厩務員や調教師が喜んでくれた、過去の良い記憶を追い求める衝動かもしれません。
それは、もしかしたら、我々が思うよりずっと高次で、誇りや名誉を懸けた戦いなのかもしれません。
どのような理由であれ、『走りたい、先頭に立ちたい』と思う衝動こそが、馬を走らせる唯一の原動力であり、だからこそ、彼らが鳴らす蹄音に我々は魂を揺さぶられるのでしょう。
さて、前置きが大変長くなりましたが、今回は、何かに役立つ情報や知識などを紹介する記事ではありません。
しかし、冒頭の『馬を水辺につれて行くことはできても、水を飲ませることはできない』という言葉が琴線に触れた方なら、感じてもらえるものがあると思います。
是非、最後までお付き合いいただけますと嬉しいです。
馬を走らせるということ
競馬において、能力の優劣は勝敗を左右するシーンは確かに存在しますが、それは2勝クラス以上の戦いの話であり、競走馬最大の壁である『未勝利クラスからの脱出』については、気性が競走馬に向いているか否かが、そのボーダーラインです。
一口馬主クラブに入会していたり、毎年POGを楽しんでいらっしゃる方なら良くお分かりいただけると思うのですが、未勝利レベルで能力が全く足りずにレースについていけないような馬って、なかなか居ないですよね?
出資馬や指名馬が勝ち上がれない時、調教師やジョッキーが話す原因の大半が、
このいずれかだと思います。
『トモが緩い』という言葉はとても便利で、スタートダッシュが効かない、道中の追走に苦労する、勝負所でギアを上げていけないなど、様々なシチュエーションの原因を一言で済ますことができます。
『トモが緩い』という現象がブラックボックス化してしまっていて、目に見える敗因がなければ、とりあえず『トモが緩い』と言っておけばいい、という風潮すらありますよね。
『トモの緩さ』とは
『トモが緩い』という現象について簡単に説明すると、トモの緩さには成長とともに改善されるものとそうでないものがあります。
通常、馬は下半身がある程度発達した状態で生まれ、上半身が成長した後に、再び下半身に成長期が訪れて、前後のバランスが整うような成長を見せます。
したがって、下半身の成長期がまだ訪れておらず、上半身に対して筋肉の発達が遅れていることが原因の『トモの緩さ』は、成長とともに改善されていきます。
対して、背中のラインが長かったり、骨盤のブレが大きかったり、馬体構造に起因するトモの緩さは改善の見込みはありません。
『トモの緩さ』については、後日詳しくまとめたものを載せますので、興味のある方は是非ご覧ください。
『馬が幼い』とは
今回のテーマで扱うのは『気性が幼い』という原因の方なので、話を戻します。
この『馬が幼い』という言い回しも同じく便利なもので、
などなど、さまざまなシチュエーションを内包しています。
『成長が足りない』という理由については、先ほどの『トモが緩い』に繋がる部分がありますが、他はすべて『気性』に関するものですね。
実は、これら『気性』に関する問題について、人間ができる対策はほとんどありません。
馬の気持ち
競走馬が抱える『気性』の問題について人間ができることは、この程度の対策か、先人の知恵を借りて馬具に頼るか、せいぜいそれくらいです。
中には、馬と通じ合うことができて、魔法のように解決してしまうスペシャルなホースマンもいますが、結局はその人独自の感覚によるもので、学べば扱えるような体系化をすることができません。
もちろん、だからと言って走る気がない馬を諦めている訳ではありません。
なんとか改善しようと試行錯誤して、結果的に上手くいくこともあります。
しかし、その方法がどの馬にも一定の効果があるものとは限らず、結局は『馬の気持ち』次第という結論に至ってしまう訳です。
一口馬主クラブの募集馬たちの中でも、能力はあるのに気性難に泣かされた馬がたくさんいます。
調教師やジョッキーと相談したり、休養先でいろいろ試してみても、全く効果がないどころか、レースを走るたびに悪化してしていくような馬もいました。
そういう時、我々ホースマンは『馬を鍛えることはできても、競走をさせることはできない』ということを痛感します。
ある調教師が話していて、強く共感した言葉があります。
走る馬は何やっても走る
走らん馬でもぎ取った1勝は格別
『試行錯誤が実ったこと』、その馬が『競走馬として現役を続けられる』ということ、『未勝利を勝ち上がるということ』が馬にとっても人にとっても、大きな意味を持っていることに改めて気付かせてくれる言葉でした。
他人の言葉を借りてばかりで恐縮ですが、2022年2月末で御引退された、名伯楽・藤沢和雄調教師の有名な言葉で「目先の一勝よりも、馬の一生」という言葉があります。
こちらも、『競走馬にとっての幸せ』とは何かを考えさせられる名言ですが、やはり、何よりも目先の一勝が必要な馬の方が多いという事実を知っていると、前者の方が、生きる意志や泥臭さみたいなものを感じます。
最後に
最後になりますが、ここまで読んでくださった『馬を愛するあなた』にお願いがあります。
人間の娯楽である『競馬』という舞台に縛られた馬たち、その競走馬になることさえ叶わなかった命たちとの別れを、悲しむことはあっても、憐れむことはしないであげてください。
調教師は、馬が心身ともに万全のコンディションでレースに臨めるように。
騎手は、馬がより速く走る助けとなるアクションや、ときには行き過ぎた衝動のコントロールを。
厩務員は、馬が心穏やかに過ごせるような良きパートナーに。
生産者は、母と共にたっぷりの愛情を注いで、愛される性格の形成を。
ファンは、馬が放つ一瞬の輝きを忘れぬよう。
『競馬』があるからこそ輝く、競走馬たちの生命に敬意と感謝を込めて、それぞれがそれぞれの役割で馬と携わって、馬と人間のより良い関係を築いていけたらと願っています。