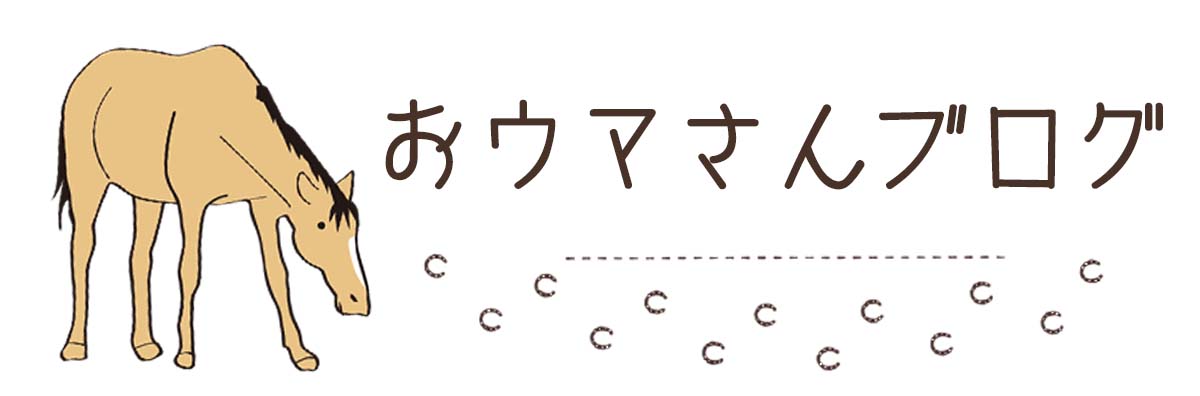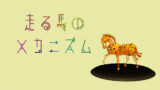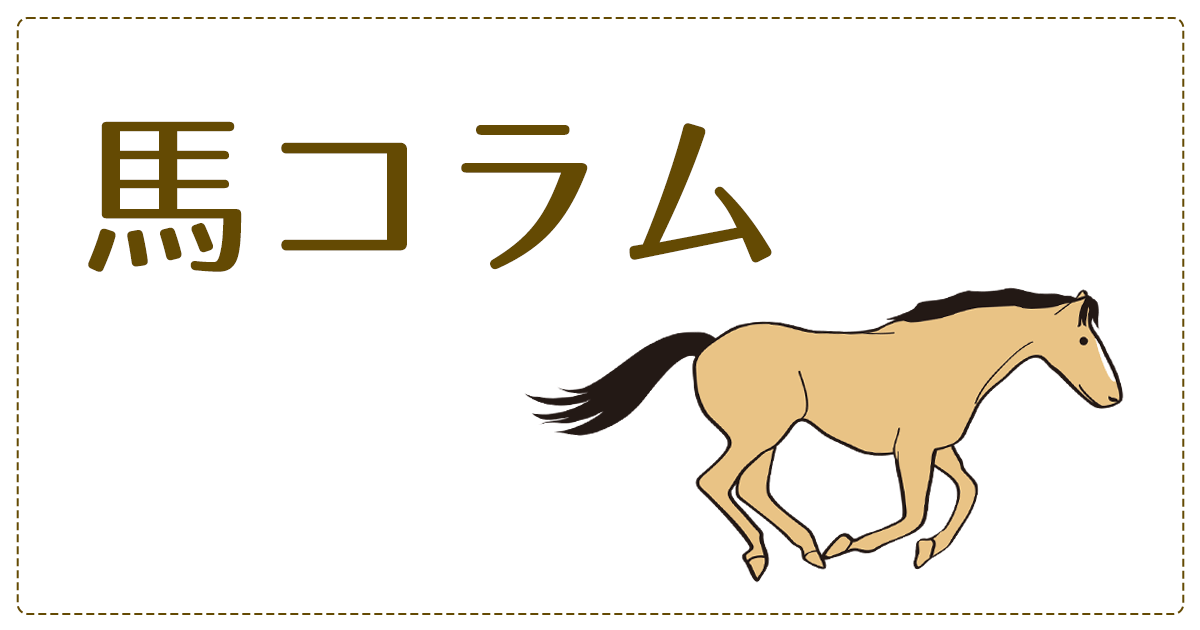鼻出血ってどんな症状なの??
今回は、競馬でしばしば見かける『鼻出血』について解説していきます。
字面だけ見れば、ただの鼻血で何故出走制限が掛かるのか不思議に思いますが、名牝『ウオッカ』が鼻出血で引退を余儀なくされたように、競走能力に大きく影響する疾患のひとつです。
この記事では、鼻出血がどのような症状なのか、なぜ馬の競走能力にまで影響を及ぼすのか、以下の目次に沿って詳しく説明していきます。
鼻出血の原因と影響
馬の鼻出血には大きく分けて3つの原因があります。
『外傷性の鼻出血』
外傷性の鼻出血は、馬房内で鼻をぶつけたり、レース中に芝の塊が飛んできて鼻に当たったりすることで、鼻腔内の血管が切れて出血することによって発生します。
我々も良く経験する鼻血で、一時的な出血で収まり、危険性はありません。
外傷性の鼻出血の場合、レース中に発症したとしても出走制限は掛かりません。
『運動誘発性の肺(鼻)出血』
運動誘発性の肺(鼻)出血は、レース中などに極度の負荷が掛かって、肺胞などの呼吸器官の毛細血管が破裂したことによる出血が、呼吸とともに鼻から噴出したものを指します。
肺組織の損傷もありますが、馬は鼻呼吸しかできないので、レース中の呼吸が上手くいかず、競走能力に大きく影響します。
十分な療養をとらないと再発するケースが多く、動物愛護の観点からも、発症後は一定期間レースに出走できなくなる鼻出血です。
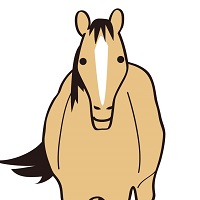
おウマたちが鼻呼吸しかできない仕組みについてはここでまとめてるよ
実は、この運動誘発性肺出血は近年増加傾向にあるようです。
福島馬主協会のWEBサイトで『松永和則獣医』がこのようなコラムを書いていました。
あくまで個人的な感覚ですが、前回お話をさせていただいた4年前と比べると、1割程度増えているように思います。
コラム「人馬一体」馬の体|福島馬主協会について
(中略)
肺出血を起こす原因については、前回お話させていただいたように、栄養価が高い飼料の摂取による血圧の変動。
さらに、細気管支炎のため細気管支血管が増幅、そこに運動によって心臓からの血液量が急増することで、毛細血管が破綻するため。あるいは横隔膜が激しく動くことによって、胸腔内の陰圧が変化するためなど、いつくか言われておりますが、特定はされておりません。
現在の競馬で勝つためには、より速く走ることが求められていることは、診察しているサラブレッドたちの体からもハッキリと伝わってきます。
より速く走るためには、様々な面において求められることが増え、さらにレベルが高くなっています。
馬の体を触っていれば、調教もよりハードになってきていることは明確ですし、カイ葉もより高いタンパク質、より高いカロリーを摂取するようなものになっています。
それらのどれか、あるいはすべてかもしれませんが、このような競走馬を取り巻く環境が、運動誘発肺出血、ひいては鼻出血を発症する馬の増加と関わりがあると考えることができます
これを読んだあとだと、よく調教師が口にする『コンディションが良い時に限って鼻出血を発症する』というジンクスも、あながち間違ったものではないように感じます。
競走馬としてのトレーニングや飼養管理が洗練されて、パフォーマンスが引き出されるほど、馬体への負担が大きくなっているというのは悲しい皮肉ですね。
鼻出血を伴わない肺出血
運動誘発性肺出血は、身体の内部『呼吸器』での出血なので、鼻出血という形で表面化しないケースもあります。
表面化していない肺出血を患っている馬は、全体の8割にものぼると言われています。
海外ではレース後に内視鏡検査による出血の有無を義務付けているところもあり、表面化していない肺出血も発見することができますが、日本では「鼻出血」という形で表面化しない限り、レースへの出走制限は掛かりません。
また、肺出血が慢性化してしまった馬には、止血作用のあるサプリメントが効果的であることが知られていますが、日本では「競馬法」によって止血剤の使用が禁止されています。
アルゼンチン共和国杯や京都記念を制した『トレイルブレイザー』は、止血剤を使用することができるアメリカに遠征して好成績を収めました。
行き過ぎた強化の制限として、使用禁止の薬剤があるのは当然のことですが、引退後の行く先が整備されていないなか、『競走馬』であり続けるための投薬は緩和されてほしいところですね。
『真菌性の鼻出血』
真菌性の鼻出血は症例自体は少ないですが、鼻出血として表面化した頃には症状が進行していることが多く、上の2つとは違い、命に大きくかかわる鼻出血です。
病巣が動脈に掛かってしまうと、突然の大量出血とともに、命を落としてしまいます。
内視鏡による真菌巣の洗浄や抗真菌薬の投与で改善がみられるケースもありますが、早期発見が必須で、普段から馬房や牧草などに気を配り、真菌への感染を防ぐほかに予防法がありません。
オススメ記事


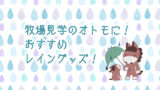
鼻出血による出走制限
鼻出血の原因や競走能力への影響はご理解いただけたでしょうか。
ここで、競馬における鼻出血による出走制限のルールについて簡単にまとめておきましょう。
JRAの公式ホームページでは、以下のように定義されています。
JRAの競走馬登録を受けている期間の競走中において、装鞍所ひき付け時から競走終了後馬場を出るまでの間に、鼻出血(外傷性のものを除く)を発症したと認められる馬は、競走の実施日の翌日から起算して発症1回目は1ヵ月間、2回目は2ヵ月間、3回目以上は3ヵ月間それぞれ出走できません。
JRA|よくあるお問い合わせ > 痼疾馬(こしつば)の出走制限とは。
つまり、JRAに所属している馬が、
装鞍所からレース終了後にコースを出るまでの間に、外傷性を除く鼻出血を発症した場合
以下の通り出走制限が掛かります。
ルール上、トレセン内での鼻出血に出走制限はありません。
しかし、肺出血だった場合はレース中も再発する可能性が非常に高く、競走成績に直結するため休養となるケースがほとんどです。
また、鼻出血を発症した馬を多く見てきましたが、1回発症してしまうと、療養を挟んでもトレセンでのレースへ向けた追い切りなどの段階で再発してしまうケースがとても多いです。
この記事を読んでくれた方には
馬の『鼻出血』は、『骨折』『屈腱炎・繋靱帯炎』とともに、競走馬生命に直結する疾病
だという認識を持っていただけると幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
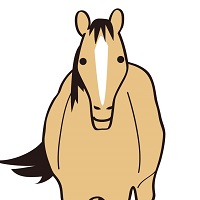
他の『馬コラム』はここから読めるよ!