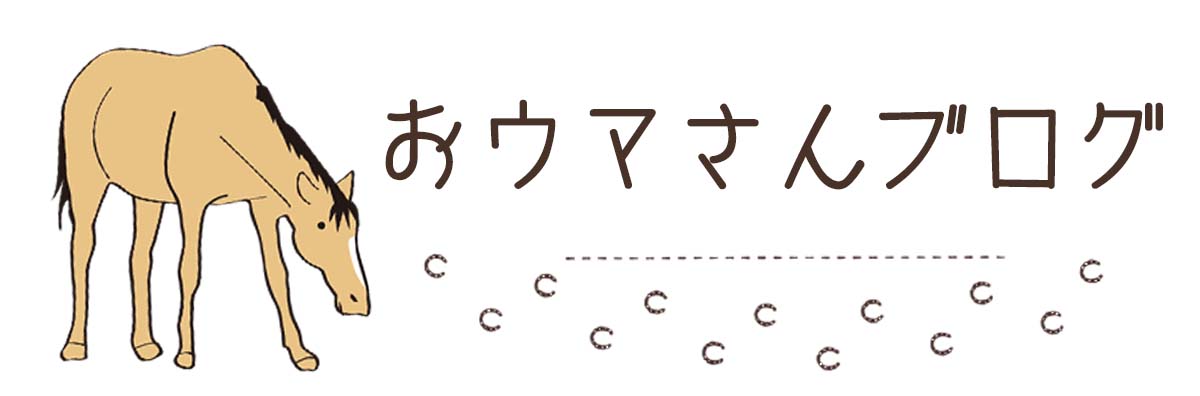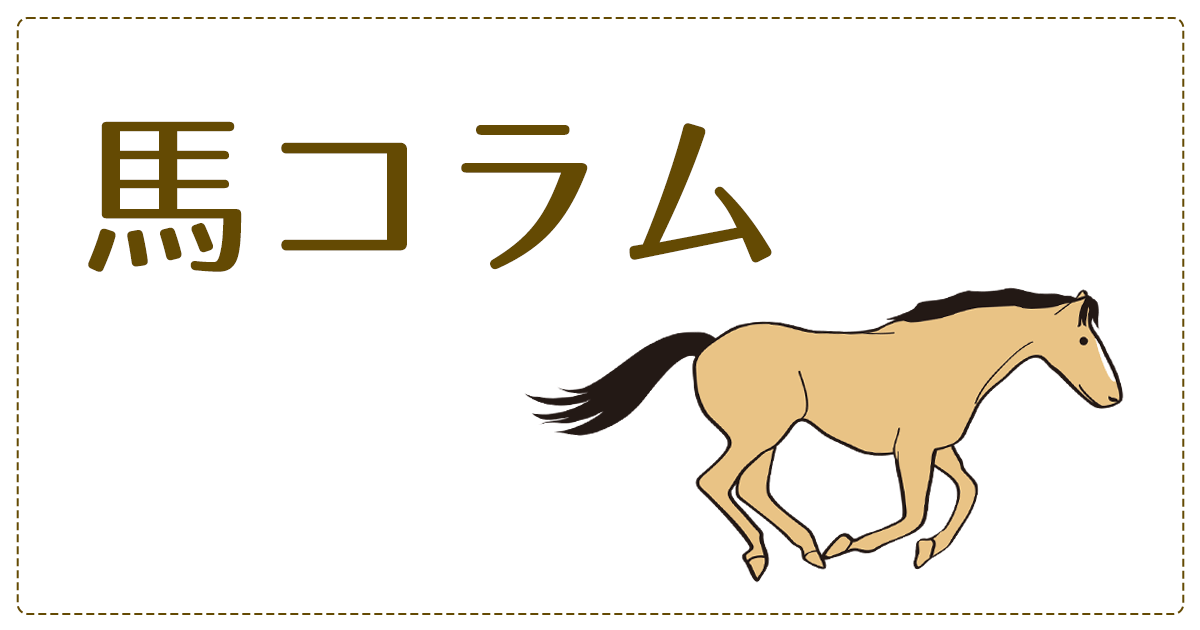馬の疝痛ってどんな症状なの??
今回は、競馬のニュースなどでよく見かける『疝痛』について解説していきます。
ひとくちに疝痛といっても、2~3時間で治る程度の軽いものから、生命にかかわる重篤なものまで、いろいろな症状を含んでいます。
この記事では、疝痛とはいったいどのような症状なのか、以下の目次に沿って詳しく説明していきます。
疝痛の種類と原因
馬の疝痛には大きく分けて5つの種類があります。
『便秘疝』の原因
『便秘疝』は、その名の通り便秘によって発生する疝痛です。
療養中などの運動不足によって代謝が落ち、腸の働きが悪くなることで、腸内に便などが滞留して発生します。
滞留中も腸壁から水分は吸収されるため、滞留物の乾燥が進んで硬くなっていき、症状がどんどん進行していきます。
症状と治療法
◇症状◇
・比較的痛みは小さく、自然解消されることも多い
・程度が悪いと数日間ボロ(糞)を出さないこともあり、腸内で便が発酵することで発生するガスによる『風気疝』も併発することがある
◇治療法◇
・ウォーキングマシーンなどで適度な運動を確保する
・多量のパラフィンオイルを流し込み、硬くなった便の排出を促す
『風気疝』の原因
『風気疝』は、腸内にガスが溜まることで発生する疝痛です。
運動不足による腸の機能低下や、発酵飼料の過剰摂取などによって、腸壁が拡張されることで痛みを生じます。
また、さく癖がある馬は空気を大量に飲み込むため、風気疝を起こしやすいです。
そのため、馬のセリでは瑕疵項目として、公表しなければいけない決まりになっています。
症状と治療法
◇症状◇
・痛みは強く、波がある。痛みが強い時は発汗することもある
・程度が悪いとガスで腹が膨れている様子が、外からでも容易に視認できる
・腸が膨張することで移動したり捻じれてしまい、『変位疝』へと変異する場合がある
◇治療法◇
・鎮痛剤の投与を行い、立ち上がったり歩行ができる状態にする
・ウォーキングマシーンなどで適度な運動を確保する
・整腸剤を投与し、腸内環境の改善を促す
『変位疝』の原因
『変位疝』は、寝返りなどの不意な回転運動で、腸の位置が変化したり、捻じれたりすることで発生する疝痛です。
『風気疝』の悪化によって変異することもあります。
症状と治療法
◇症状◇
・激しい痛みを伴い、発汗する
・軽度であれば、運動によって自然に腸の位置が戻る
・重度の場合は、捻じれによる圧迫で血流が止まり、腸組織が壊死し、死に至る
◇治療法◇
・ウォーキングマシーンなどで適度な運動を確保する
・開腹手術で捻じれを治す。壊死した組織がある場合は切除して、正常な組織同士を縫合する
『痙攣疝』の原因
『痙攣疝』は、極度な興奮や寒冷状況に晒されたり、強度の高い調教による疲労などによって、腸の動きが異常に活発になることで発生する疝痛です。
症状と治療法
◇症状◇
・比較的痛みは小さく、自然解消される
・腸の動きが活発になるため、腹部に耳を近づけると「ゴロゴロ」と音が聞こえる
◇治療法◇
・痛みによるストレスで、さらに興奮が進んでしまうので、鎮痛剤の投与によってストレス源を解消する
『寄生疝』の原因
『寄生疝』は、回虫や条虫などの寄生虫が腸内に寄生することによって発生する疝痛です。
寄生した虫によって症状が異なります。
症状と治療法
◇症状◇
・痛みが表面化する頃には、症状がかなり進行していることが多く、手遅れとなる
◇治療法◇
・定期的かつ計画的な駆虫薬の投与で防ぐことができる
その他の疝痛
その他の疝痛の代表例として『胃潰瘍』が挙げられます。
日本の競走馬の内、約70パーセントの馬が胃潰瘍を発症していると言われています。
その主な原因はトレーニングや長距離の輸送によるストレスによるものです。
また、本来は牧草などの青草を食べて生きる草食動物であるにもかかわらず、競馬に耐えうる体力やエネルギーを蓄えるために、穀物中心のエサを食べていることも、消化器官に負担を掛けています。
ホースファーストの精神
エサによる消化器官への負担については『競走馬』という側面上、仕方のないことではあります。
しかし、トレーニングや輸送によるストレスは人の手で改善ができる要素です。
日本では、ヨーロッパ諸国のように、ホースファーストの精神の醸成がまだまだ足りません。
週末の競馬やパドックを見て、競走馬は『ピリピリしていて危険』という印象をもつ方も多いかと思いますが、ヨーロッパに行くと驚くほど落ち着いている馬が多いです。
最近では、SNSの発展やウマ娘などの影響で、世間の目が少しずつ馬に対しても向くようになってきました。
今まで馬業界では当たり前だけども異常だったことが、世間の感覚に触れて、時には目に晒されて少しずつ改善されていくことを願っています。
オススメ記事


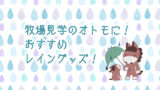
馬の内臓はリスクだらけ
馬の内臓は、腹膜に包まれた状態で背骨からぶら下がっていて、一部を除いて固定がされていません。
しかも、人間は二本足で立つので、骨盤というしっかりとした支えがありますが、馬をはじめとする四足歩行の動物は、細く隙間だらけの肋骨以外に骨格による支えとなるものがありません。
腸捻転は防ぐことができないのか?
内臓が背骨からぶら下がって不安定な上に、腸膜が不完全なので、馬の腸は運動や寝返りなどで頻繁に位置を変えています。
そもそもの構造的に、腸捻転のリスクがとても高い動物です。
毎年たくさんの馬が腸のトラブルで命を落としていますが、早期発見が必須なことと、開腹手術に耐える体力も必要で、未だに決定的な解決策は見つかっていません。
疝痛を起こしやすい消化プロセス
馬が疝痛を起こしやすい要因は他にもあります。
同じ草食動物でも、牛は4つの胃を駆使して消化するのに対し、馬は腸で消化します。
つまり、牛は消化器官の前半で消化が進行しますが、馬は腸(特に大腸)まで消化されずに食べ物が運ばれてきます。
腸は胃よりも圧倒的に複雑な構造ですから、消化できていない食べ物は詰まりやすく、疝痛を起こしやすい消化プロセスとなっています。
また、牛よりも馬の方が腸が発達しているかと思いきや
『馬:約30メートル』 『牛:約50メートル』
と、メインの消化器官でもスペック負けしています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
馬は構造的に疝痛を起こしやすい生き物であることがおわかりいただけたと思います。
馬を注意深く観察し、些細な仕草の変化などのサインを見逃さない
正直なところ、我々にできることはこれくらいですが、24時間365日、常に見ていることはできません。
”これくらい”のことの実現がとても難しいのも現状です。
なにか決定的な改善策が出てくることを切に祈っています。

最後まで読んでいただきありがとうございます。
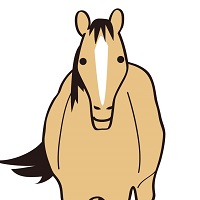
他の『馬コラム』はここから読めるよ!