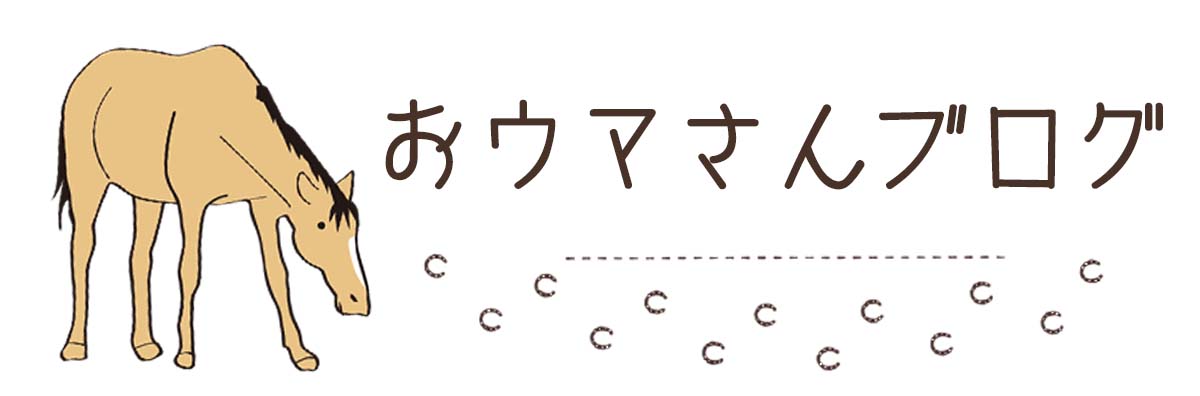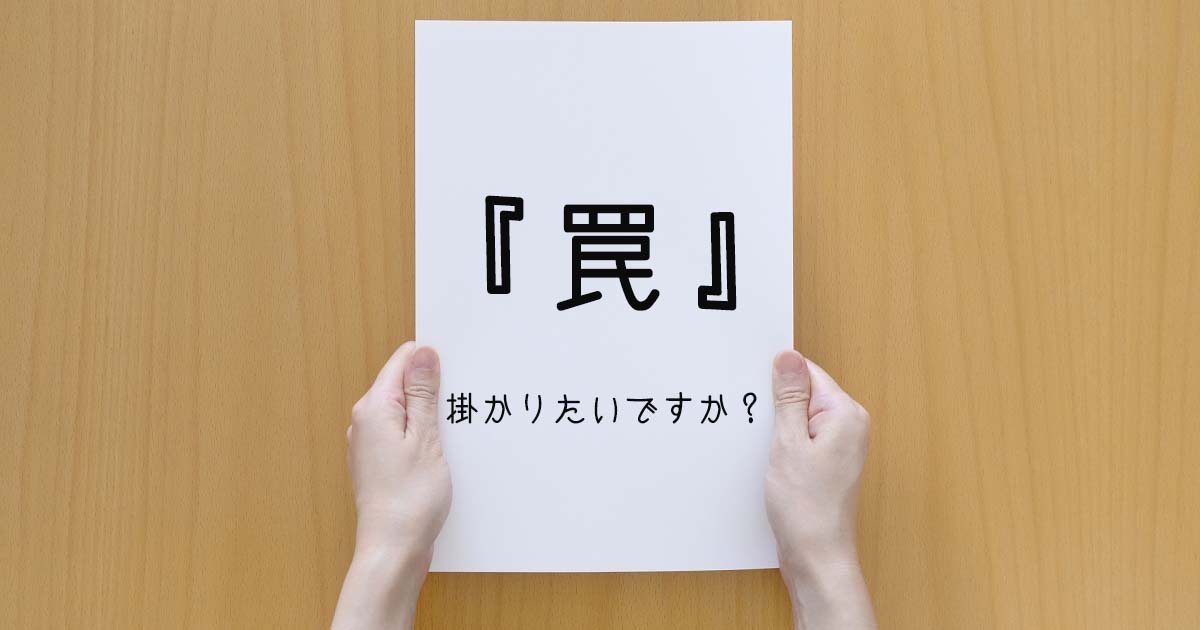こんにちは、おウマです。
今回は馬体診断講座6回目です!

『走る馬の条件』とされている指標について、別の視点から切り込んでいきます

POG指名や一口馬主の出資馬で悩んでるひとは要チェックだよ!
走る馬の条件を疑う視点を持つ
『馬体診断講座』6回目の今回は、今までと少し毛色を変えて、一般的に走る馬の特徴として捉えられている『左後一白』という特徴が持つ落とし穴と、『トモの踏み込み』を盲信することの危険性について解説していきます。
この記事を読めば、あなたのPOG指名馬や一口馬主での出資馬の底上げに役立つ視点を身に付けていただけます。
また、馬体写真があれば誰でも簡単に判別できるものなので、是非最後までご覧ください。
『左後一白』と『トモの踏み込み』の盲信にご注意!
走る馬の条件とされている『左後一白』と『トモの踏み込み』が良い馬。
先人たちが、長年の経験則に基づいて導き出した指標ですが、こんなリスクも孕んでいます。
それぞれの項目について、なぜそのようなリスクを孕むのかを解説していきます。
オススメ記事


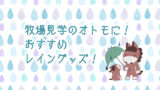
肢部の白斑と蹄の色
左トモのみ白斑があることを『左後一白』と呼びます。
左後一白は複数の名馬に見られる特徴であるために、走る馬の証であるとされ、馬体診断において重要視されています。
また、左後一白に限らず肢部白斑があることで目印となり、脚捌きが良く見えるというメリットもあります。
『肢部白斑』による落とし穴
しかし、育成場やトレセンでは歓迎されるだけの要素ではありません。
白斑部分の皮膚は他の皮膚と比べて弱く、順調な調教の妨げとなります。
特に繋ぎ部分に白斑がある馬は注意が必要です。
調教中は着地時に球節が沈み込むことで、繋ぎの裏の皮膚が伸長するだけでなく、ウッドチップやダートと球節が擦れて切れることがあります。
さらに、冬場の調教後はお湯で洗うことで皮膚表面の油分が落ち、あかぎれの様な症状に悩まされる馬が出てきます。
そしてこれらの症状は、圧倒的に繋ぎに白斑がある馬に集中します。
また、体調が優れずに代謝が落ちている時などに、吹き出物のような皮膚炎を発症することがありますが、肢下部に症状が出ることが多く、これも白斑を持つ馬は出やすい上に長引くケースが多々見受けられます。

装蹄師泣かせの蹄
肢部に白斑を持つ馬のリスクは他にもあります。
白斑が蹄冠部に掛かる馬の多くは白い蹄を持ちます。
白蹄は正常な黒い蹄と比較すると角質が柔らかいため、踏み掛け(他馬や自分で肢を踏むこと)で蹄に内出血を起こしたり、蟻洞になりやすかったりと、蹄疾患を発症しやすい特徴を持ちます。
また、柔らかいがゆえに釘の掛かりが甘くなるため、落鉄も起こしやすいです。
釘穴が広がって別の場所に打つ→落鉄→また別の場所に打つ、と繰り返して蹄がボロボロになってしまうことがあります。
走り方の癖による蹄の変形も起こしやすく、まさに『装蹄師泣かせの蹄』と言えます。

一口馬主で出資馬を選定する際に、肢部白斑があるだけで除外すべきだとは毛頭思いません。
しかし、『甲乙つけがたい馬から一頭を選ばなければならない』、という時の一押しとして参考にしていただきたい馬体診断の項目のひとつです。

これは意外!
左後一白ってすごい特徴なんでしょ!?
それが弱点になっちゃうなんて

そうだよね!
特に蹄は馬にとってとても大事な器官だから、強いに越したことはないと思うよ
『トモの踏み込み』の深さのヒミツ
一口馬主クラブの仕事をしていた時、会員の方から『トモの踏み込みが良く見えたので出資を決めました。』というご報告を度々いただきました。
一口馬主クラブの募集に携わった者としての個人的な見解の域を出ませんが、人間に従順な馬に対しては曳き方やプレッシャーの掛け方次第で、いくらでもトモの踏み込みは調整できます。
急かされても踏み込んで歩くことができない馬や、急かすことができない性格の馬を選択肢から外す馬体診断法としては使えるかもしれませんが、歩様動画における『トモの踏み込みが良い=走る』という説を妄信することは良くない傾向です。
それよりもリズムよく歩くことが出来ているか、首を上手く使って歩いているかの方が、遥かに大事な診断項目と言えるでしょう。
まとめ
この記事では『左後一白』と『トモの踏み込み』に潜む罠~と称して、走る馬の条件とされている項目を盲信することの危険性について解説しました。
記事の内容を簡単にまとめると
『左後一白』を含む、肢部白斑がある馬は皮膚が弱い
白い蹄は角質が脆い
『トモの踏み込み』は曳く人の技量で調整できる
皮膚の弱さと蹄の脆さは、順調な競走馬生活を送る妨げになります。
トモの踏み込みの良い馬を盲信しないでほしいという件については、一つの美点にとらわれずに、総合的に馬体診断をすることが重要であるというメッセージを込めました。
最後に、『馬体診断講座』で解説している馬の見方の記事一覧を載せています。
すべて読破いただければ、簡単に馬体診断ができるようになるようにカリキュラムを組んでいますので、是非ひとつひとつ読んでいただければ幸いです。
すでに独自の馬体診断理論をお持ちの方は、気になる項目があればクリックすることで対象の記事を読むことができますので、新しい知識や視点をピックアップしていってください。